私たちの食生活には欠かせない油。
現代人は昔の人よりも何十倍も油を摂取していると言われています。
その中でも気をつけたいのが、どんな油をどのくらい、どのように摂るかです。
今日はそんな中で気にするべき油、オメガ3脂肪酸について書いてみたいと思います。
油の種類と特徴
油は主に
- 飽和脂肪酸(バターなどに豊富)
- オメガ3脂肪酸(青魚やアマニ油・エゴマ油に豊富)
- オメガ6脂肪酸(大豆油やコーン油などに豊富)
- オメガ9脂肪酸(オリーブ油などに豊富)
大きく分けると4種類に分類されます。
私たちの食事で特に多く使われる油は、植物油です。外食でふんだんに使われる安い油も、この分類に入り、オメガ6を多く含む油です。意識的に減らさないと、すぐに口に入ってきてしまう油です。
反対に、意識しないと口に入ってこないのは、オメガ3の油です。熱に弱いため炒め物や揚げ物で使えないので、意識的に青魚などで摂取したり、品質の良い亜麻仁油や荏胡麻油を生のまま口に入れることをしないとほとんど摂れません。
オメガ6とオメガ3のバランスが重要
このオメガ6とオメガ3の2つの油はなんと、お互いに正反対の役割を担っています。
例えば、オメガ6は白血球を活性化して病原菌などと戦う働きをしますが、オメガ3は逆に白血球の働きを抑制、炎症を抑えることがわかっています。
だから、オメガ3とオメガ6のどちらがいい油、悪い油というわけではなく、常にバランスを意識することが重要、健康のためにはどちらも欠かせないのです。
世界中の様々な疫学調査から、血液中のオメガ3:オメガ6のバランスが、1:2になることがベストだと言われています。
では、なぜ1:2くらいが良いのか?そのメカニズムはまだよく分かっていませんが、人間だけでなく自然界で健康的に生きる野生動物などは概ねオメガ3:オメガ6が1:2程度になっています。中には、オメガ3の方が多い動物もいますが、オメガ6が過剰な生き物というのは人間以外にはほとんどいないようです。
オメガ3とオメガ6の比率を整えるには
では、どうしたらオメガ3:オメガ6の比率を1:2に近づけられるのでしょうか?
現代の食生活ではまず、オメガ6は意識的に減らしていく必要があると多くの研究者が提言しています。
反対にオメガ3は日頃から意識的に増やす必要があるので、日本人なら、昔から食べてきたイワシ・サンマ・サバのような青魚を積極的に食卓に出すことを意識したり、魚がなかなか食べれない地域の人や苦手な方は、クルミなどのナッツや、チアシード、アマニ油やエゴマ油などを使うのも有効です。
えごま油の効能
①血液サラサラ効果
えごま油に多く含まれるオメガ3脂肪酸の代表的な働きに、血流の改善があります。血管をしなやかにし、血流の流れをスムーズにする効果があるといわれ、血栓(血管内で血液が固まる)ができにくい状態にすることで、血圧やコレステロールを下げるなど、生活習慣病の予防になる栄養素です。
②脂肪燃焼・代謝促進
油=太るというイメージをもってしまいがちですが、えごま油に多く含まれるオメガ3脂肪酸には、身体を温めて代謝を活発にし、脂肪を燃焼しやすくする効果があります。
③心疾患や認知症の予防効果
オメガ3脂肪酸は、身体の中に吸収されると「DHA」と「EPA」に変化します。これらは、脳細胞の活性化や情報の伝達性を高め、認知症や高血圧など様々な疾患に効果があるとされている有効な成分です。また、うつ病などの心疾患にも良いといわれています。
④アレルギーの改善効果
アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギーは、体内に入った抗原(アレルゲン)を排除しようと、免疫が過剰反応することでおこります。「DHA」は、こうした過剰反応の原因となる物質の生成を阻害することで、アレルギーを抑える効果があるといわれています。
えごま油のおすすめの摂取方法
当店で販売している無化学肥料・無農薬の国産荏胡麻を生搾りした荏胡麻油。現代人にうれしい健康効果がたくさんあります。
現代人に著しく不足しているといわれているオメガ3脂肪酸は体内で作ることができない必須脂肪酸です。その中でも最も多くの含有量をもつえごま油だから、スプーン一杯で一日の必要量を摂取することができるのです。
オメガ3脂肪酸は熱に弱い特性があるため、加熱しないでご利用ください。
サラダやパスタなどの洋食から、お味噌汁、冷奴などの和食、ヨーグルト、パン、コーヒーなど、さまざまな味付け、食材のお料理にかけてお召し上がりください。
しも農園 宮崎県三股町で育った貴重な 純国産 えごま油 生搾り 100g



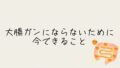
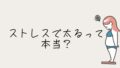
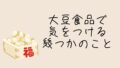
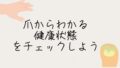
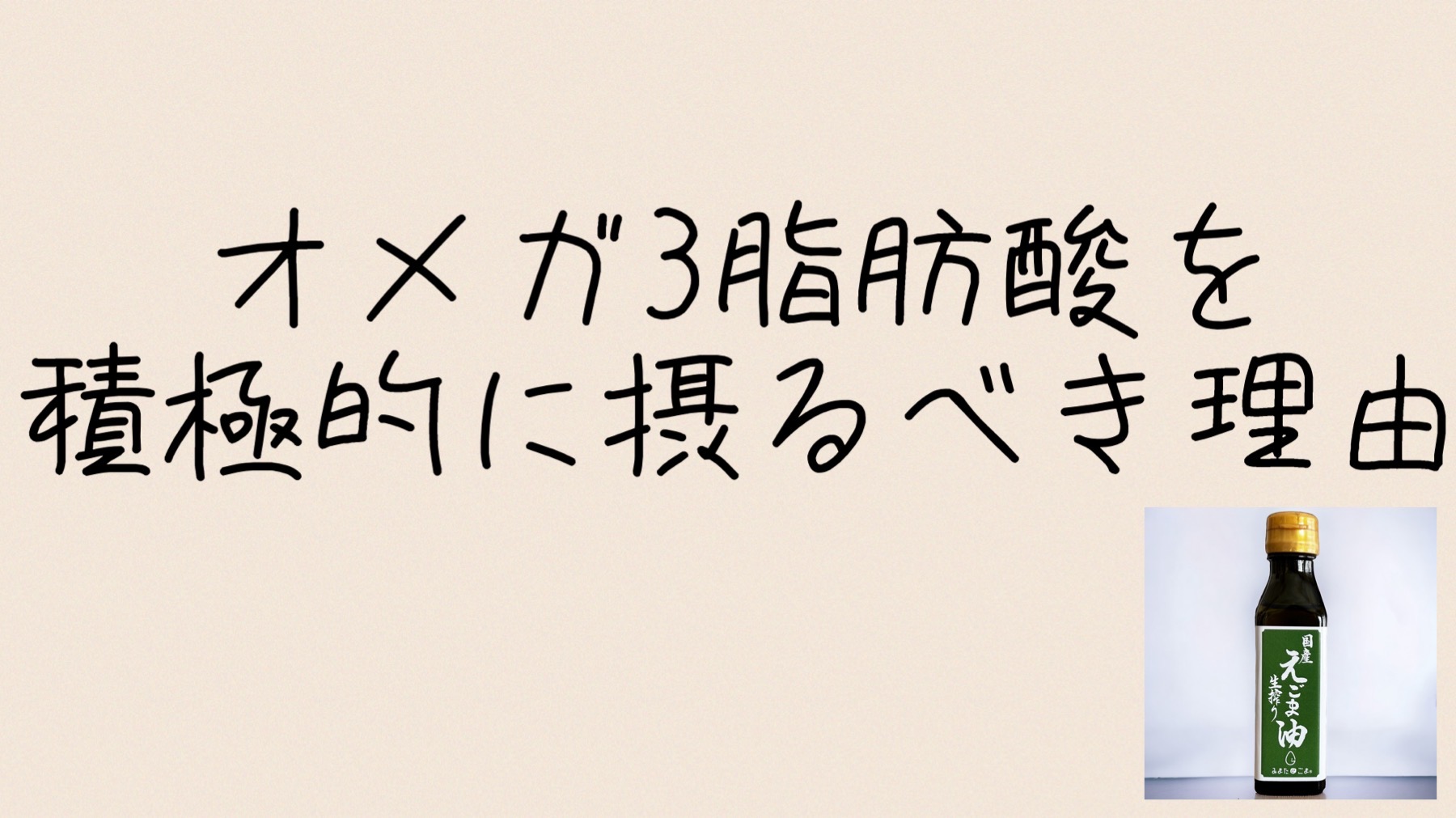
コメント